誤診/誤診一歩手前
- HOME
- 誤診/誤診一歩手前
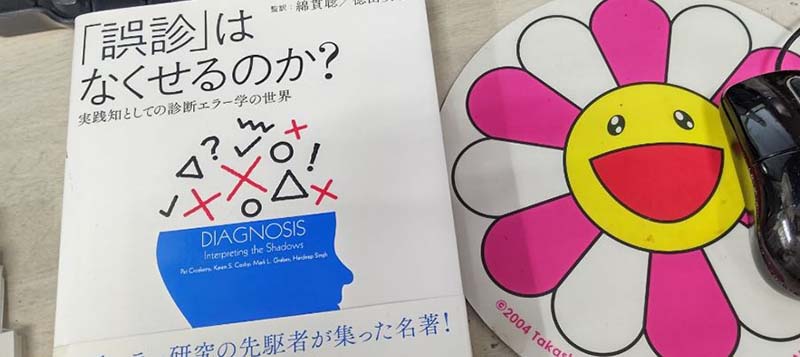
誤診は、なくなりません。私も毎日します。でも、誤診ってなんでしょうか?
誤診の有名な話
東京大学医学部の名誉教授の有名な話があります。その医師は、退官の際に、自分の誤診率は14.2%と発表しました。同僚医師たちは、その数字の低さに驚き、患者はその数字の高さに驚きました。
獣医師と飼主間での誤診の認識の違い
飼主にとって誤診とは、直ちに適切な医療や検査がおこわなれなかったという主観的な事実ですが、獣医師にとっての誤診は、その時点では、適切だと思って行った医療行為が、時間の経過の中で、実は間違っていたという客観的な事実です。
言葉遊びで、誤診を考える
獣医師が、『この薬を飲まないと、治らない』と言ったとします。これは、『この薬を飲んだら、治る』とは、まったく違った意味です。薬という言葉を、宝くじという言葉に置き換えたら、違いが、わかります。宝くじは、買わないと当たりませんが、当たらなかったからといって、『宝くじは買わないと、当たらない』は嘘にはなりませんね。『この薬を飲まないと、治らない』が獣医師の考える一般的な獣医療のイメージで、薬を飲んでも治らないからといって、それは誤診でもなんでもありません。次の段階への重要なステップと考えてください。
獣医療における日常的な誤診?
全科診療で、言葉の話せない動物を相手にする獣医療特有の誤診のパターンです。
① 私のよくする誤診
下痢のひどい子が来院したとします。慢性の下痢・・・何か重篤な疾患が隠れている下痢・・・は2~3週間持続する下痢と定義されます。まず数日様子をみて、その後継続的な症状があれば、食物アレルギー、寄生虫、ガン、免疫疾患 etc.・・・・の中から、経験的に発生率の高そうな疾患を考慮して、ひとつづつ、『薬を飲まないと、治らない』を実践していきます。その過程で、飼い主のいう誤診は、常に発生しています。
② 間違いではないけど
犬は心臓病が多い動物です。多くの犬の心臓病は聴診で発見可能です。聴診をして雑音が聴取されれば、多くの獣医師は、心臓病と診断して、投薬が始まります。しかし、心臓の検査には、心臓エコーが最も有用で、エコーで調べると、単なる心臓病が、●●心臓病と定義され、数十%の確率で、薬が異なってくる可能性があります。
③ 大変な事態になったケース
②で、心臓病の話をしましたが、このタイプの話は、神経疾患でもしばしば起こります。例えば、ダックスの歩行障害が来院したときに、MRI検査までは実施せず、胸腰部椎間板ヘルニアとして、治療を 開始するケースは日常です。以前に、ダックスではありませんが、ヘルニアと診断し、脳腫瘍だったケースがありました(忘れられない症例の項目参照)。
④ 診断キットに頼りすぎる誤診
当院に転院してきた致死性の疾患で最も多いものは、犬の胆嚢破裂です。多くが、前の病院で膵炎と診断されてきました。これは明らかに、簡易膵炎診断キットの普及が招いたものです。膵炎診断キットは、感度は高いですが、特異度は低いです。胆嚢が破裂し、炎症が膵臓に及んだ結果、2次的に膵炎が発生したものを、原発性の膵炎と診断し、重篤になったケースです。おそらく転院しなければ、膵炎が原因で死亡したと言われて終わるでしょう。
2021年、コロナが教えてくれた誤診
近代医学は、一つの原因と、その結果を、ある病気と解明することによって成立してきました。しかし、コロナは、コロナウイルスが主(最初の)原因かもしれませんんが、3割は無症状で、多くは軽症・・・つまり、コロナ感染症というのは、存在論ではなく現状は認識論となります。そうすると、コロナ感染症は、コロナ+他の要因 →→→ 発症+他の要因 →→→ 重症化となり、ウイルス感染単独では語られないと、定義されます。そのような認識論の世界では、『無症状コロナを、認識できないのは誤診か?』、『無症状コロナ状態を、治療しないのは、医学的には如何に定義されるか』という、誤診、医療過誤の新しい問題が出てきます。
情報のスピードの速さが招く誤診
1950年代には、医学の情報が2倍になるのに50年かかっていたそうですが、2020年には、たった73日で倍になるそうです。私も、この文章を書いている2021年に、まったく知らない3つの病気に出会いましたが、初めは誤診していました。20年間臨床の世界にいますが、おそらく、知らない病気・・・・・つまり、初診時には誤診する病気は、まだまだ山のようにあると思います。ちなみに、3つの病気は、レイバー症候群、サンドホフ病、脊髄くも膜のう胞でした。
・Challenges and Opportunities Facing Medical Education
忘れられない症例
① あやうく
犬の症例。ガウガウで、まったく触れない犬でした。聴診も無理。飼主の、狂犬病ワクチンだけでも接種して欲しいという依頼でした。なんとか咬まれないように注意し接近して、ワクチンを接種しようしたその時、ワンと吠えた後、発作で死亡しました。接種後であれば、ワクチン接種のせいになっていたと思います。忘れられない症例。
② 去勢手術後
犬(M・ダックス)の症例。去勢手術2日後に、嘔吐。手術は問題なかったので、軽~く、様子を見てくださいと伝えました。しかし、容態が急変して、運ばれてきました。レントゲンを撮ると、なんと陰嚢に腸がはまり込んでいました。もともと腹膜に穴が開いていて、その穴は精巣でガードされたのですが、去勢で精巣をとったので、その穴から腸が出てきたということです。以来、抜糸までは手術の成功ではないなと、今一度、気を引き締めることになった症例。
③ 炎症性乳がん
犬の症例。犬の炎症性乳がんは、手術をしてはいけない乳がんとして現在有名です。手術の刺激で、劇的に病状が進行するからです。さて、まだその名前が知られていない1,990年代、その症例に手術を実施して、最悪の事態になった経験があります。誤診・手術の失敗と言われて、かなり辛かった。私は、その標本を私は保存して、数年後、まさに炎症性乳がんであったことを確認しました。私は、力及ばなかった症例は、必ず血液や組織(標本)を保存しています。10年後に、誤診の理由がわかることもあります。飼主さんも、納得がいかない時は、血液保存、解剖などを依頼すべきです。
④ 死後の検査で確認
保護猫の嘔吐の症例。閉院直前に来院。一般状態が良かったので(よく見えたので)、嘔吐止めを注射して、治まらなければ翌日検査を実施する予定でした。帰宅後、虚脱して死亡。注射を間違って死亡させたと言われました。しかし。遺体を死後に検査して、胸水があることが確認。心筋症、FIPなどを疑いましたが、当時はそれ以上の追及は無理でした。初診時に、どこまで高額の検査を実施するかは、永遠の獣医療のテーマです。③でも書きましたが、納得のいかない場合は、遺体の検査も実施すべきです。
⑤ どこかが痛そう
未去勢犬の症例。どこかが痛そうということで、検査をするとひどい前立腺肥大。去勢手術をして前立腺は小さくなったが、食欲がもどらず。入院して観察すると、なんと癲癇(てんかん)。飼主が、てんかんを、痛みだと思っていた症例です。その後、状態は急速に悪化して死亡。脳腫瘍の疑いの症例でした。飼主の言葉を、どう理解するか、本当に考えさせられた症例。
⑥ 口が痛そう
猫の症例。よだれが少しあって、口の中が痛そうということで来院。歯肉炎もあったので、それが原因かなとも安易に考えたけれど、飼主が、絶対に普通じゃないというので、専門医に紹介。専門医も一度は異常無しとしたけれど、飼主の強い要望で再検査したら、なんと舌の裏に小さな癌を発見。飼主の強い言葉がなければ、最悪な事態になっていたかもしれないというトラウマの症例。⑤とは真逆だけど、飼主の言葉にしっかり耳を傾けようと改めて思った症例。
⑦ それはないよね
犬の症例。犬が、急にフラフラで立てないとのこと。高齢犬によくある、特発性前庭疾患(眩暈のようなもの)かなと思って、治療。翌日、家族の一人が、病院に(こっそり)電話をかけてきて、『実はお酒を飲ませました』って。そういえば、吐物が、大学の時の飲会での臭いだったんだよね。犬の酔った症例は初めて見ました(めっちゃ詳しく前庭疾患の説明したので、恥ずかしかった)。
⑧ 食事が原因
犬の症例。健診でKが異常値。Kは命に係わる重要な項目。年齢なみの若干の腎機能の低下はあったがそれにしても、おかしい。希少な症例を考慮し、治療をするも改善しない。ある時、ふと飼主が、この子、バナナが好きで・・・、健康を考えて、野菜と果物中心の自家製食なのに病気になってって・・・。あああああ、食事が原因だったわけです。食事指導で、すっかり数値は改善しましたが、獣医師が自家製食を嫌うのはそういう経験が少なからずあるからなんですよね。自家製食にこだわる食事に熱心な飼主には、以後、相当注意しています。ペットに詳しいと思って調理しているところが厄介で、しばしば最悪な事態になります。
⑨ 解剖で疾患名が判明
猫の症例。嘔吐を繰り返す、小さな猫さんでした。通常の検査(血液検査、エコー検査、バリウム検査)ではわからず、かなり体力の消耗も激しいかったためCT検査もできず(CT検査は、全身麻酔になります)、死亡。死後解剖で、胃の幽門部にリンパ腫(ガンの一種)があることがわかりました。内視鏡検査も、猫が小さすぎて、できなかったと思います。同じ症例がもう一度来ても、多分、診断できないと思います。
⑩ 脳・神経系の疾患
この分野の疾患は、町医者には、ほぼ精査は無理だと実感します。結局、CT/MRI検査を同時に実施しないと、わかりません。ダックスの歩行障害で椎間板ヘルニア・・・・コーギーの歩行障害でDM・・・・と診断してたら、結局脳腫瘍だったとか。猫の癲癇(テンカン)症例が水頭症だったとか・・・・。心臓エコー検査をしなけ心臓疾患がわからないように、レントゲン検査をしなければ呼吸器の疾患がわからないように、CT/MRI検査をしなければ、脳・神経系はわからないものです。
⑪ ワクチンを信じすぎると
猫の症例。子猫の時に、2回ウイルス性白血病の検査を実施して陰性。その後、白血病予防ワクチンを毎年接種していた子が、白血病になったという症例。初診時から、みるみる症状が悪化して死亡。前記のように、経歴上は、白血病を疑う余地はなったのですが、亡くなる直前に、もしやと思って検査したら、白血病陽性・・・・衝撃でした。自宅から脱走経歴があり、その際に感染したのだと思います。後年、某ワクチン会社と共同研究をした時に、意外と、白血病ワクチンに反応しない個体が存在することを知り、ショックでした。ワクチンが効いていなかったのです。白血病の検査は高額で、ワクチン接種した子に実施することは、医療費の面で本当に躊躇します。
まだまだ思い出の症例は沢山あります。しかし、よくよく考えると、誤診だとこちらが気が付くのは、飼主が転院をせず最後まで当院を信じて通院てくれたからです。亡くなた後に、原因追求をさせてもらったり・・。飼主が転院をなさると、治療ですっかり調子が良くなったとこちらは勘違いして、誤診したままですからね・・・・。技術、経験、信頼関係・・・名医への道は、一生かかる(それでも成れないけど)。
トラブルを回避して死に向き合う
獣医師側と飼主との誤診のトラブルは、獣医療の認識体系上、必ず発生します(忘れられない症例を見てください)。獣医師は間違った治療はしていないが、飼主の立場にたてば、(獣医師側からみれば、言いがかりだとしても)その言い分もわかることが、実はほとんどです。残念ながらペットが死亡し、もしその時に誤診を疑うならば、死後の検査(直後であれば遺体のレントゲン、エコー等)、血液の保存の依頼、解剖を実施しましょう。飼主と獣医師の信頼関係があれば、獣医師は、できる限りその子の死の原因に向き合ってくれると思います。

 お問い合わせ
お問い合わせ

 お問い合わせ
お問い合わせ